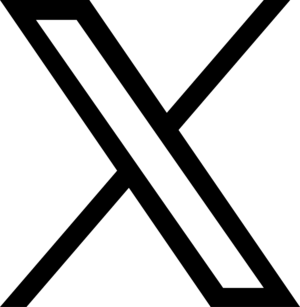NOVELあなたに恋してもいいですか?

試し読み
第一話 カフェ・スペラーレで執筆します
わたし――築城《つきしろ》 奏《かなで》は大学の講義が終わったあと、必ず立ち寄る場所がある。
こぢんまりとしたカフェ・スペラーレ。
イタリアの国旗や、ヨーロッパと思しき写真や風景画が飾られている。
店内には女性オーナーと、アルバイトの女性店員がひとり。
そんなカフェの最奥、角の席がわたしの定位置。
ここにいると落ち着くし、癒やされる。
わたしは十三インチのノートパソコンを開き、文書作成ソフト『月太郎』を起動した。
とあるジャンルの小説家になるべく、毎日の執筆を欠かさないようにしている。
カフェの外をたまに通る車の音。
お湯が沸くコポコポという音。
そして、わたしがキーボードを叩く音。
ほかのお客さんの声はあまり耳に入ってこない。ただひたすら目の前のことに集中する。
「あの……もうすぐ閉店なのですけど……」
心の奥をくすぐるような美声が聞こえて顔を上げる。
そこにはカフェオーナーの美希《みき》さんが立っていた。
まわりを見まわせば、ほかのお客さんだけでなくアルバイトの店員さんももう帰っていて、店内には美希さんとわたしのふたりだけだった。
じつは、こういうことがよくある。
わたしは頬が熱くなるのを感じた。
閉店時間間際になるまで気がつかなかったことと、いま美希さんとふたりきりだということをひどく意識してしまう。
美希さんに話しかけられると、ちょっと緊張する。
「子どもを迎えにいってくるだけなので、お客様さえよければここでこのまま続けられても大丈夫ですよ? 筆が進んでいらっしゃるみたいなので……」
美希さんがにこっと笑う。ウェーブのかかった茶色い髪に、大きな瞳。
頬は薔薇色で、唇はぷるぷるだ。
見とれそうになるのをなんとかして堪《こら》える。
「えっと、じゃあ……お言葉に甘えて、そうさせてもらいます」
わたしが頭を下げると、美希さんはほほえんだまま「わかりました」と言った。
「扉には一応、鍵をかけていきますね」
「はい、ありがとうございます。行ってらっしゃい」
美希さんは扉の札を『CLOSE』にして、外から鍵をかけた。
お子さんがいたなんて、知らなかった。
どんなお子さんだろう。あれだけの美人オーナーなのだ。きっとかわいい。
どんどん妄想が膨らんでいく。
……って、そうじゃなくて。書かなくちゃ!
わたしはふるふると首を振って、キーボードの上に両手を置いた。
カタカタと音を立てながら文字を打ち込んでいく。
しばらく集中していた。
鍵が開くガチャッという音と、カランコロンという鈴の音が聞こえる。
カフェの扉が開いて、美希さんが顔を出した。その後ろから、女の子がひょっこりと現れる。
薄茶色のふわふわした髪の毛。ぱっちりとした二重まぶた。
かっ、かわいい!
それに美希さんとよく似ている。美希さんが子どものときは、こんな感じだったのかな。
女の子はわたしと目が合うと、颯爽とこちらへ歩いてきた。どこか日本人離れした顔立ちなので、ハーフかあるいはクオーターかもしれない。
「こんにちは!」と女の子が大きな声で挨拶してくれる。
「こんにちは。あの、ありがとうございました。帰りますね」
わたしが帰り支度をはじめると、女の子は不思議そうに首を傾げた。
「ごはん、たべていかないの?」
「うん。もうお店はおしまいなのに、わたしがお邪魔しちゃってたの」
「だいじょうぶ! にかいで、ごはんがたべられるよ!」
女の子の無邪気な顔を見ていると、自然と顔がほころぶ。ほほえましい。
「もしよかったら、どうぞ。お夕飯でも食べていってください」
「えっ、でも……」
「毎日、来てくださって本当にありがとうございます。ほんのお礼に、ね?」
美希さんの笑顔はきらきらと輝いているように見える。
「こっちだよ!」と、女の子に手を引っ張られる。
「えっと、じゃあ……お邪魔します」
第二話 カフェの二階へお邪魔します
女の子に手を引かれ、深みのある茶色い木階段を上って二階へ行く。
白いレースのドアカーテンの下を通って部屋へ入る。
「ごめんなさい、散らかっているけれど」
「いえ、とんでもないです」
実際、美希さんが言うほど散らかってなんていなかった。おもちゃや絵本など、物は多いがきれいに整頓されている。
「ねえ、こっち」
女の子に服の裾を引っ張られて歩く。リビングの隣が女の子の部屋だった。
「おねえさん、あそんで。わたし、ひとりっこだから、ママがごはんをつくっているあいだ、ヒマなの」
「うんうん」
「だからね、おままごとしよう?」
「えっ」
おままごとなんて、いつぶりだろう。
「おねえさんは、あかちゃんね!」
「わたしが?」
「そう! りあんがママだよ」
そういえばわたしも、子どものときはママ役をやりたかったな。
『ママ』は子どもにとって母であり、憧れの存在でもある。
そうして『おままごと』が始まる。
「あかちゃん、ねんねしましょうね~」
はじめは寝ていればよかったので楽だった。
女の子は「あかちゃんがねているあいだにごはんつくりましょ」と言っておもちゃの野菜を切っていた。
「あっ、あかちゃんがおきたわ! あかちゃんはね、バブーってなくの」
女の子が目線で訴えかけてくる。「泣きなさい」と。
「バ、バブ~……」
とんでもなく小さな声になってしまった。
「はずかしがっちゃ、だめよ! あかちゃんは、そんなふうになかない!」
ごもっとも!
たとえ遊びのおままごとだとしても、真剣に取り組むべきだ。
わたしは「すぅ、はぁ」と深呼吸をした。息を整えて、赤ちゃんになりきろうとする。
「バブゥ~~!」
わたしが大声で叫んだ瞬間。美希さんがやってきた。きょとんとしている。
頬に熱が集まっていく。いや、耳にもだ。
恥ずかしすぎる!
妙な汗が出てきた。美希さんの顔を見ていることができなくなって下を向く。
「ありがとうございます。里杏《りあん》と遊んでくださって」
「あ、いえ……。あの、敬語じゃなくていいです。わたし、まだ大学生で……あっ、築城 奏といいます」
いまさら名乗るのもなんだかおかしな話だ。美希さんもそう思ったのか、くすくすと笑っている。
「そういえばまだ自己紹介もしてなかったわね」
美希さんとわたしはカフェのオーナーと、その常連。
カフェには一年ほど通っていて、顔見知りではあるけれどお互いに苗字は知らなかった。
「湯元《ゆもと》 美希と、里杏よ。奏ちゃんは大学何年生?」
名前で呼ばれた!
それだけで舞い上がってしまう。
優しくてきれいな美希さんにはずっと憧れてきた。もっと近づきたいと、思っていた。
「奏ちゃん?」
「あ、えっと……わたし、大学二年生です。文学部の」
「そうなの? もしかして虎月大学?」
この街で大学といえばそこだ。わたしが「はい、そうです」と答えると、美希さんは満面の笑みで「私、そこの経営学部の卒業生よ」と教えてくれた。
「じゃあ先輩なんですね」
「ええ、だいぶんね」
美希さんって何歳なんだろ?
気になるものの、聞いてもよいのだろうか。